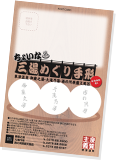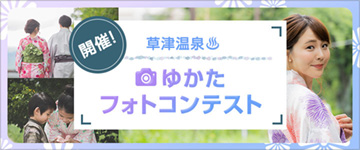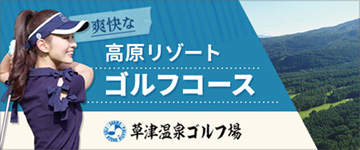名湯 草津温泉を満喫草津三湯めぐり
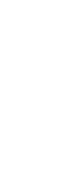

- 大滝乃湯・御座之湯・西の河原露天風呂
- 草津温泉に数ある共同浴場の中で、大浴場や大型露天風呂を有する代表的な共同浴場が「草津三湯」と呼ばれる、大滝乃湯、御座之湯、西の河原露天風呂。もちろん三湯全ての湯船が源泉かけ流し。
草津の湯を堪能できる草津三湯めぐりをお楽しみください。

お知らせ

日本屈指の名湯
草津温泉
恋の病以外効かぬ病はないとの
言い伝えがあるほど、効能高い草津温泉。
天下の名湯を満喫してください。
- 草津温泉の正しい入浴法はこちら
- 硫黄をたくさん含む草津温泉はpH値2.05という強い酸性のお湯です。正しい入り方を知って草津温泉の効能を存分に楽しもう!

日帰り草津温泉
ちょいな
三湯めぐり手形







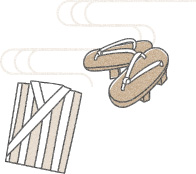
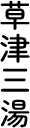
昔の湯治文化を現代に再現
御座之湯
悠久の歴史の中で、良質の湯により栄えてきた草津温泉。草津のシンボル湯畑に再建した御座之湯は、冬住みをしていた江戸~明治の建物を再現し、木造にこだわり、杉板を使用した 「とんとん葺き」の屋根と漆喰の壁からかつての趣が漂います。
詳しくはこちら



 Instagram
Instagram


 Language
Language